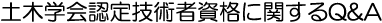 |
|
|
このQ&Aは、会議での議論や提案者である岡村議長の話をもとに作成したものです。したがって、このQ&Aにない質問や、あるいは答えの表現で不透明な部分がある場合があります。今後、皆様から寄せられた意見によって修正・加筆し、HP情報の更新時に訂正版を掲載していく予定です。
(2000.11.1 技術推進機構:五老海)
A.添付資料6「土木学会技術者資格制度の創設について」の(1.資格制度設立の理念と目的)をご覧下さい。
A.この制度設立準備のために、「土木学会認定技術者資格評議会」を設置することが平成11年度第8回理事会で承認されました。委員の選出母体は土木学会のほか、中央官庁、地方公共団体、関係学協会、その他から参画いただき、真に公正・中立な観点から土木技学会認定の資格が有すべき要件を検討し、認定や運用方法などについてとりまとめ、理事会に提案することになっています。
A.土木学会会員のためにつくるものです。会員の中で希望する方が対象です。
なおQ1でお答えしましたとおり、この制度が有効に活用されることによって21世紀の社会で尊敬されるような土木技術者の資質向上を図り、技術あるいは技術者の流動化がより一層進展する国際社会で活躍しようとする会員が不利益を被ることがないようにつくるものです。 A.資格の階層は4段階が適当と考えています。(添付資料7をご覧下さい)
土木技術者が担う公共事業は市町村レベルの比較的小規模なものから国家的な大プロジェクトまであります。また会員の勤務形態も公共事業の企画立案や発注を担当する側の会員、工事を請負い実施する受注側で活躍する会員、さらには技術の開発研究や人材を育成する教育機関に活躍する会員など各種多様です。これらの現状を踏まえ、将来にわたって真に有用な土木技術者の資格はどうあるべきかを会員の皆様と一緒に考えて、種類、レベル等最善の資格を定めたいと思います。 A.将来は、先進諸国の資格との相互承認を念頭において修士課程修了者レベルに基準においた制度としていくのが望ましいと考えていますが、現状から考えて経過措置として5年間程度は次のようにすすめてはどうかと考えています。(添付資料7をご覧下さい)
・土木技術者資格4は全分野共通のもので、土木技術に関する基礎的知識を有する技術者資格で、大学土木工学分野の教育プログラムの修正またはそれと同等の水準にある者。 ・土木技術者資格3は、土木学会会員歴が3年以上の者で、少なくとも1つの専門分野における実務経験が4年以上ある者で、より上位の資格保持者のもとで自己に与えられた業務を遂行する能力と責任を有する技術者の資格をイメージしています。(例えば、コンクリート工学分野では、土木学会の「コンクリート標準示方書」の本文と解説を理解している水準)。 ・土木技術者資格2は、土木学会員歴が3年以上の者で、専門分野での実務経験が10年以上ある者で、自己の判断力をもって部下を指導監督し、与えられた事業の遂行のみならず関連する技術の蓄積や環境への影響など後世への教訓などについて提言できる能力を保持している技術者。(例えば、コンクリート工学分野では、コンクリート標準示方書の本文及び解説の知識に加え、構造工学あるいは建設マネジメントに関する知識を有する水準)。 ・土木技術者資格1は、フェロー会員である者が取得できる最上級の資格とし、専門分野における知識経験が極めて高く、他分野の課題に対しても自己の責任をもって適切な指導・助言できる能力を有する技術者の資格。 などをイメージしています。 A.土木学会で体系化されている7つの専門部門と共通分野を入れた次の8部門を専門領域とし、各部門の中で資格が必要と考えられるものを部門所属の各調査研究委員会の協力を得ながら検討したいと考えています。
その部門は次のとおりです。 第1部門 構造系 第2部門 水系 第3部門 地盤系 第4部門 計画系 第5部門 コンクリート系、材料系 第6部門 施工系、マネジメント、エネルギー系 第7部門 環境系 第8部門 共通系 A.資格は、土木学会が土木技術者として必要な知識・能力を社会に保証するものですから、資格審査委員会(仮称)の認定が必要です。審査は、筆記試験で判定できる知識とともに実務経験、継続教育も重要な条件となります。なお、それぞれの段階における認定は次のようにイメージしています。将来的には上位の資格を取るためには下位の資格を有することを条件としますが、経過的措置として、当分の間いずれの資格からでも取ることができるように認定方法を定めたいと思います。
・土木技術者資格4(全分野共通):大学の土木工学系分野の教育プログラムを終了しているか、またはそれと同等であることを筆記試験等で資格審査委員会が認定する。 ・土木技術者資格3(専門分野):当該分野における専門知識を十分に有していることを面接及び継続教育終了証明書の確認、または筆記試験により資格審査委員会が認定する。 ・土木技術者資格2(専門分野):当該分野において10年以上の実務経験を有することを書類審査と面接により資格審査委員会が認定する。 ・土木技術者資格1は、フェロー会員(フェロー審査委員会の審査があります)を対象とする資格で、極めて高い専門性を有し、広範な知識経験が極めて高いことを当該専門委員会が認定する。 A.土木学会会員を対象とした資格ですから会員歴を重視します。各資格と会員歴の関係はおおよそ次のように考えていますが、なお検討中です。
・土木技術者資格4は、土木技術者としてスタート段階の全分野共通の資格ですので会員であることは必要ですが会員歴は問いません。 ・土木技術者資格3は、例えば3年以上、第2段階も3年以上、第1段階はフェロー資格と同様に20年以上の会員歴を必要と考えています。 A.同一段階の資格の登録有効期間は5年程度を限度にしてはどうかと考えています。また登録更新はその間の継続教育による取得単位証明書により行なうことを考えています。なお、より上位資格の取得についてはQ7でお答えしたとおりです。
A.資格が社会の評価を得、長く存続していくためには、その活用が適切、有効に行なわれる必要がありますが、資格制度をつくる段階で何らかのインセンティブを与えることは考えていません。社会に技術者の責任を明確にしていくことがこの資格のもつ意義でありますので、原則として、使われ方は関係方面に任せたいと思います。ただし、規制緩和が進む中で、この資格にどのような使われ方があるかについて検討し、有効な活用を関係方面に働きかけていく努力をします。例えば単に工事の現場を受け持つ受注者側の活用のみではなく、発注者支援の資格、あるいは教育・研究機関関係者での活用も視点においた検討を行い、評議会に相談したいと考えています。
A.活用方法が定まり、社会的に評価されるまでの期間は特にありませんが、少なくとも土木技術者個人の技術レベルを中立・公正な機関である土木学会が保証したことは、技術や技術者個人の流動化がますます激しくなる国際社会にあって、国内のみならず広く海外で活躍する場合に多くのメリットを生むのではないかと思います。また現在までの社会は、技術者の所属する会社などの組織が信用・評価されてきましたが、21世紀の社会では、所属する組織・機関ではなく、技術者個人が評価され、信用されることが重要な時代になるとおもいますが、このような時代に「土木学会認定の資格」(専門家集団である土木学会が個人を保障すること)の有用性は高まってくるものと考えています。
A.技術士や施工管理士などの国の資格、あるいはRCCMやコンクリート技士などの民間資格などはそれぞれ歴史を持ち、社会で貢献してきているものですが、土木学会の資格創設にあたってはこれら既存の土木系各種資格との調整や整合性は考えておりません。少なくとも資格創設時点ではこれらの資格とは切り離して議論したいと思っています。
学会認定資格の理念、目的はQ1に述べたとおりですが、この資格は単に工事を請け負う受注者側の技術者のみを対象にしたものではありません。発注者支援あるいは教育研究機関に所属する会員個人の技術レベルを中立・公正な専門家集団である土木学会が保証することにより、会員が所属する組織の技術力が客観的に証明されることにもなります。 A.技術士をはじめ既存の各種資格はそれぞれの役割を果たしていると思います。この現状に学会としての意見を申し上げることは適切ではありません。
ただ、資格を取る側、資格を活用する側、の意見を常に把握し、時代を見据えた資格のあり方などを学会は常に調査研究し、その結果に基づいて適宜適切な改正を行い、時代の求める土木技術者の資質向上とこの資格システムの一体化によって社会の付託に応えるような努力が必要であると考えます。 A.資格制度が確立した段階で、アメリカの土木学会(ASCE)やイギリス土木学会(ICE)など、海外協力協定国(現在16カ国と締結しています)の土木学会と協議し、資格の相互承認などを進めたいと考えています。
A.土木学会認定資格はわが国工学系学協会で最初のものですので、多くの注目を浴びるものと思います。また一度つくった制度がその目的をどのように達成するかも関心の的になるでしょう。
21世紀の新しい土木技術者が社会的義務と責任を果たし、社会からの信頼を得て広く活躍するためのこの制度を会員一人一人と協力しながら育てていく努力が大切と考えています。 A.Q4でお答えしました4段階の資格の中で、土木技術者資格4(全分野共通)については本年内に実施要綱を定め、平成13年度の早い時期(できれば13年10月中旬)に実施することとして準備を進めます。また寄り上位の資格についても専門委員会の協力により、準備が整った部門から同時期に試験が実施できればよいと考えています。
また土木技術者資格1はフェロー審査委員会との調整をすすめます。 以上
最初のページへ戻る (C) Japan Society of Civil Engineers
|